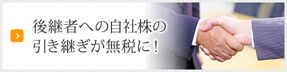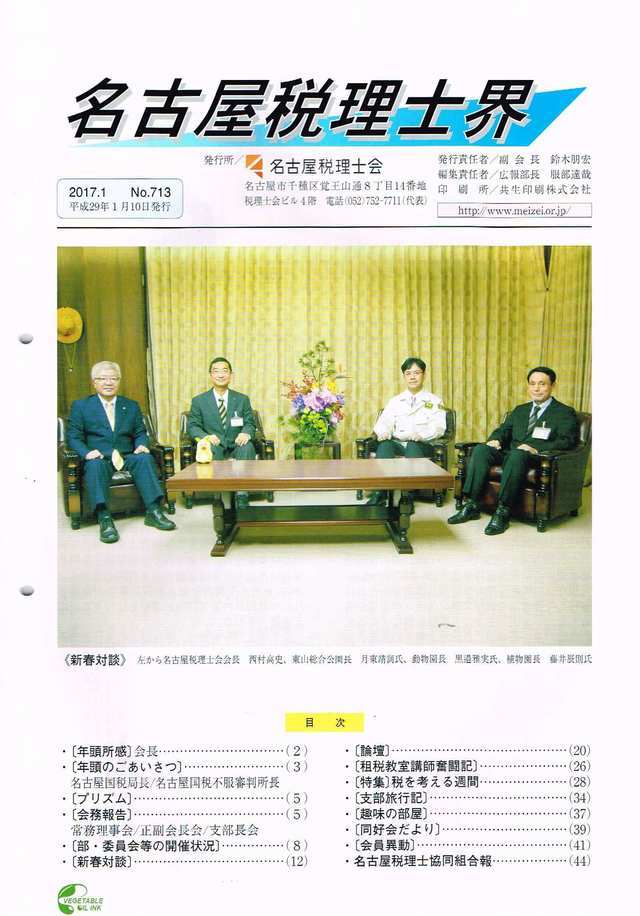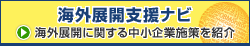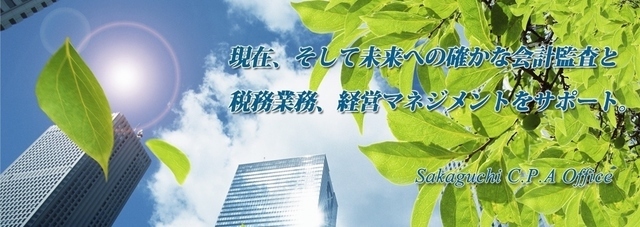相続・事業承継のご相談なら、愛知県大府市の坂口美穂公認会計士事務所・資産税務コンサルティングにお任せください。
相続税の節税対策のポイント
「相続」というものを考える際に、大きくは次の3つの検討課題があると思われます。
① 財産を円満に分割する。  円満な遺産分割
円満な遺産分割
② 相続税をできるだけ少なくする。  節税対策
節税対策
③ 無理なく相続税を支払う。  納税資金対策
納税資金対策
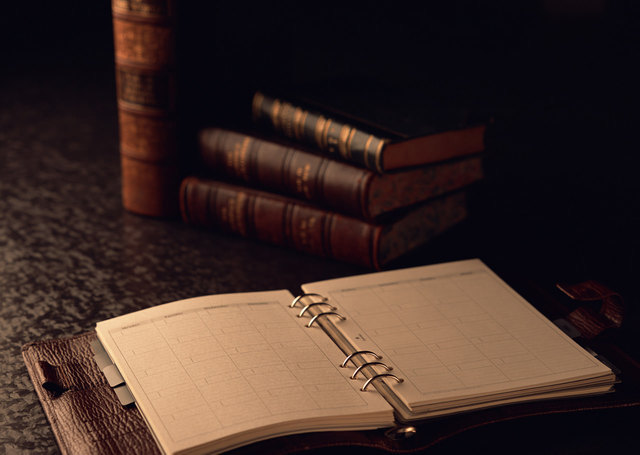
これらは、個々に検討して解決していくものではなく、うまく組み合わせることによって、節税対策だけでなく、事業や財産の承継をスムーズに行えるようにすべきであり、そのためには納税資金も確保しておく必要があるといえます。
したがって、相続の問題を考える場合には、まず現状を把握したうえで、被相続人の意思を尊重しつつ、どの財産を誰に相続するのかある程度の方向性を決めながら、節税対策と納税資金対策を進めていく必要があります。
それでは以下、具体的に『相続を乗り切るためのチェックポイント』を解説します。
現状の把握
まず、相続税と納税資金について、下記の手順で試算します。この場合、まずは財産を整理しておくことが重要です。自分の財産をどうしたいのかを考えれば、次の世代へ承継してもらう方向性も見えてくるのではないでしょうか。
そして、下記のフローチャートでの各チェックポイントにおいて問題となりそうな、あるいは既に問題となっている部分について、次の「円満な遺産分割」「節税対策」「納税資金対策」で具体的に検討していくことになります。
ダウンロード関連資料
円満な遺産分割

 財産の分け方をなるべく早く決め、その分け方に関して意思表示をしておく
財産の分け方をなるべく早く決め、その分け方に関して意思表示をしておく
遺言書がない場合は、相続人で財産の分け方を協議し、その内容を「遺産分割協議書」として作成しなければなりません。ところが、具体的な分割が決まらず、相続税の申告までに「遺産分割協議書」が作れなかった場合、次のようなデメリットが生じます。
・ 配偶者の税額軽減の特例
・ 小規模宅地の評価減が利用できない
・ 延納方法を選べない(共有財産のままであるため)
・ 預金や株式を勝手に動かすことができない(共有財産のままであるため)
・ 保険金の支払いが受けられない(共有財産のままであるため)
遺産分割には、現物分割・換価分割・代償分割の3つの方法がありますが、財産目録を作成し、それぞれの相続人の事情を考慮して分割していきます。常に自分(被相続人)の考え方や希望を周りの人に伝えているなら、うまく伝わるかもしれませんが、しかし、得てして伝わらず、やはり誤解や争いのもとになりかねません。
しかし、遺産分割は遺言があれば、基本的に遺言どおりに行われことになります。したがって、被相続人の思い通りの相続をスムーズに実現させるために、被相続人はなるべく早め(生前)に、遺産の分割方法を決め、その分割方法について遺言書(公正証書が無難)を作成しておくことが望まれます。
 次に託す代表者を決めて伝えておく
次に託す代表者を決めて伝えておく
相続の手続きは相続人全員で進めなければなりませんが、窓口となる代表者は1人のほうが何事もスムーズに行きます。その代表者を選任しておくことが大事です。
 共有名義は避ける
共有名義は避ける
納税資金捻出のための売却用の相続財産でなければ、単独名義で財産を分けておいたほうがよいでしょう。単独名義であれば所有者の意思で利用が可能ですが、所有者が2人以上だといろいろ複雑な問題があるため、現実の利用は難しいといえます。
 配偶者の取得分を決める
配偶者の取得分を決める
配偶者の税額軽減の特例は、非常に優遇されておりかつ一度だけの特権ですから、うまく利用することで納税負担額が軽くなります。ただし、次に予想される配偶者の相続(二次相続)を考えると、無税となった相続税は一時的に繰り延べられたに過ぎないということもあります。こういった税金面と、その他いろいろな事情を踏まえ、配偶者の取得分を決めていく必要があります。
 土地を分筆する
土地を分筆する
いずれ分割するのであれば、早めに相続人の間で意思を確認し、分筆してしまったほうが相続税は安くできます。
 代償分割を行う
代償分割を行う
特定の相続人が財産を取得し、他の相続人はその代償となる金銭を支払う方法です。
不動産が分割できない場合はこの方法が有益です。また、相続人が現金を希望しても遺産の中に分けるだけの現金がない場合は、いったん特定の相続人が取得し、不動産を売却して現金に換金して分けるということになります。
 納税用の財産として売却用の土地を決める
納税用の財産として売却用の土地を決める
取得した相続財産だけでは相続税を支払えない場合は、納税資金は別のところで確保する必要があります。そこで、売却用地等を決めて、必要な相続人が共有持分で取得する方法をとります。ただし、当該売却用地の売却代金が相続税以上になると、譲渡所得税が課税されますから、なるべく譲渡所得税がかからない持分割合を決めます。
また、事前に売却活動を始めていれば、売却価格の予想がつけられますので、現実の手取額を逆算することもできます。安易に法定割合などで決めてしまわずに、最後まで節税の可能性を探りましょう。
節税対策
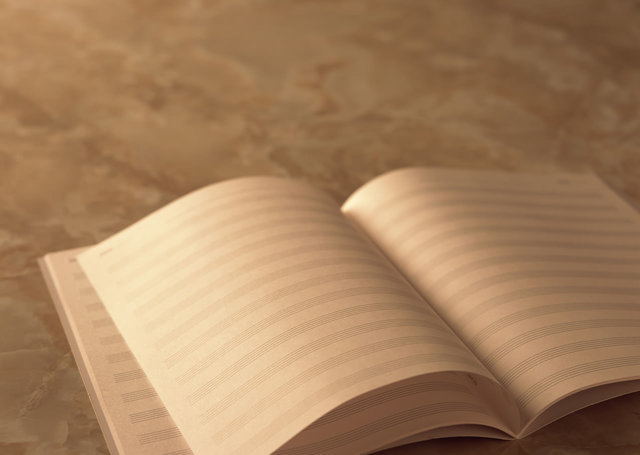
 相続人が増える要素はないか
相続人が増える要素はないか
相続において、法定相続人の数はとても重要です。人数が多くなればしれだけ、さまざまな控除枠が広がるからです。法定相続人が増えると、次のようなメリットが生じます。
・ 総資産についての基礎控除枠が増える
・ 生命保険金や死亡退職金の非課税枠が広がる
したがって、戸籍謄本等を今一度見直し、法定相続人のカウント漏れがないかどうかを確認してみましょう。また、生前に孫やお嫁さんと養子縁組などを相続人を増やすことにより、上記のような節税対策に取り組むのもよいでしょう。
 土地の評価減の可能性を探る
土地の評価減の可能性を探る
土地には下記の点を考慮して評価減の可能性を探ります。
・ 間口、奥行き
・ 不整形地、のり地、がけ地の有無
・ 宅地が接している道路
・ 私道の有無(通り抜けができるか)
・ 実際の面積(測量で実際の面積を知る)
・ 小規模宅地の特例が使えるか(下記ダウンロード資料参照)
・ 生産緑地の評価減が使えるか
・ 宅地の有効宅地率(大きな土地の評価は下げられる)
・ 不動産鑑定評価(特殊な土地は個別評価で下げる)
・ 仮登記の有無
 土地を人に貸してしまう
土地を人に貸してしまう
貸家建付地の評価減、負債などによる減額などで確実に節税効果はありますが、「借金しておけば相続対策に有利」というのは過去の話です。こういった賃貸業を行う際は、他物件と差別化して一定の賃貸収入を得る工夫が必要で、綿密な収支計画を立て、長期の安定経営が絶対条件となります。
 非上場株式の評価減の可能性を探る
非上場株式の評価減の可能性を探る
ご存知のとおり自社株の相続税評価額は単価×数量で成り立っています。そこで、相続税評価額を引き下げる方法も単価面と数量面でのアプローチが基本となります。その対策を以下の体系図(下記ダウンロード資料参照)に示すと、このとおりとなります。
 贈与や寄付で財産を移す
贈与や寄付で財産を移す
財産贈与(相続時精算や課税制度など)売却処分、寄付などで財産を減らすことも、相続税の節税対策になります。
暦年課税か相続時精算課税かの選択
親から子(又は孫)への贈与については、暦年贈与と相続時精算課税制度を選択できますが、実際、どちらの制度を選んだほうがよいのかは、一概には判断がつかないのが現状だと思います。あくまで目安ですが次のことが言えると思います。
 相続税がかからない若しくはかかっても少額の場合は、相続時精算課税制度が有効
相続税がかからない若しくはかかっても少額の場合は、相続時精算課税制度が有効

暦年贈与で何年もかけて財産を移転するのに比較し、早期に多くの財産移転が可能で、仮に贈与税を支払った場合、相続時に還付される可能性大。
 相続発生まで長期間贈与が可能な場合は、暦年贈与が有効
相続発生まで長期間贈与が可能な場合は、暦年贈与が有効

長期間かけて多くの財産の贈与移転が可能で、相続時に相続財産の加算も基本的にない(相続開始3年以内の贈与は加算)。
 贈与を受ける人がまとまった資金を必要としている場合は、相続時精算課税制度が有効
贈与を受ける人がまとまった資金を必要としている場合は、相続時精算課税制度が有効

贈与を受ける人が多額の住宅ローンを抱えている場合等、贈与資金で一括返済できる場合の金利負担の減少効果は大きい。現金等については、贈与時の価額も相続時の価額も基本的に変わらないため、相続時精算課税の適用の有無による損得はない。
 財産規模が大きく多額の相続税がかかる場合は、初期から中期は暦年贈与、後期は相続時精算課税制度が有効
財産規模が大きく多額の相続税がかかる場合は、初期から中期は暦年贈与、後期は相続時精算課税制度が有効

暦年贈与から始めることで、ある程度の財産を移転できる。
その後、相続時精算課税制度を適用し収益物件(賃貸マンション、アパート等)等を贈与することで、贈与を受けた人に収入が入り被相続人の現金収入の蓄積(相続税の対象)も防げる。また、後期に相続時精算課税制度を使った贈与を行うことにより贈与物件の値下がりリスクも小さい。
ダウンロード関連資料
納税資金対策

 納税資金や遺産分割金を確保しておく
納税資金や遺産分割金を確保しておく
お金は急に増やせません。事前に生命保険で納税資金を準備したり、不動産や有価証券等を換金して分けられる状況を作っておくとよいでしょう。また、納税資金を土地の売却資金で充当する場合は、申告日に売却が完了していることが理想です。そのために逆算すると申告日の半年ぐらい前から売却活動に取りかかり、納税の全体像を把握する必要があります。
さらに、賃貸事業等で安定収入を作っておくことも対策の1つとなるでしょう。
 延納を利用する
延納を利用する
申告日に納税資金が準備できない場合は、とりあえず延納手続きをしておきます。ただし、延納は延滞利子税がかかり、かつ延納から物納への変更はできません。
 物納を選択する
物納を選択する
現金で納付できない場合で下記のように売却価格より評価のほうが高い場合には、物納を選択するほうが有利です。
(不動産売却見込額-譲渡経費-譲渡所得税及び住民税)<(相続税評価額-物納経費)
物納の手続きは1年近くかかりますが、その間の利息がかからないため、負担は少ないといえます。また、上記のとおり延納から物納への変更は不可能ですが、物納から延納への変更は可能ですので、とりあえずは物納が認められそうであれば、まずは物納申請を検討し、状況をみて延納等に変更するといった対策も考えられます。
 銀行借入も視野に入れる
銀行借入も視野に入れる
返済計画が立てられるのであれば、相続税と費用を合わせた額の借り入れをすることも方法の1つです。
 賃貸事業で返済する
賃貸事業で返済する
相続税の納税資金を金融機関で借り入れた場合、長期の借入金を返済する原資があれば安心です。土地を所有している人の場合は、賃貸事業を計画し、その手取分で借入金を返済していくことも可能です。
この計画が実現すると今までの収入を投入することなく、土地を売却することもなく、返済していくことができます。ただし、借り入れは相続税と建築費の両方になりますから、しっかりした事業計画と、その額に見合った担保が必要になります。
 譲渡税は払わない
譲渡税は払わない
相続税を払うために土地を売却した場合には、相続税を取得原価として計上できるので、その分利益から除外され、譲渡税は少なくすみます。また、土地を売却するのが1人ならその人の相続税しか引けませんが、売却地を共有にし、相続税をなるべく多く原価にしたほうが譲渡税はさらに少なくなります。さらに、売却価格から原価と相続税と諸費用を引き、残りの利益が100万円以下であれば、譲渡税はかかりません。したがって、売却の際は、納税額を確保し、かつ譲渡税がかからないぎりぎりの割合で持分を決めるのが得策です。ただし、この特例が適用できるのは申告後3年間となっていますので、売却するならこの期限内が有利です。
また、譲渡税の特別工場は年間1人当たり100万円です。売主が多くなるほど、特別控除の額が増やせるということになります。持分のある全員の確定申告が必要になり、手間はかかりますが、節税につながります。
 更正の請求
更正の請求
申告が終わったあとも1年間は更正の請求で相続税を減らせるチャンスは残されています。たとえば、路線化で評価をして申告をしたところ、鑑定評価等で評価減できることが分かれば、更正の請求をすることによって、相続税を減らすことができます。

お問い合わせはこちら
当資産税務コンサルティングは、公認会計士・税理士 坂口美穂事務所が運営しております。
相続税、贈与税、譲渡所得税等の資産税対策、そして事業承継対策や海外展開について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

ご不明点があればお電話ください
よくあるご質問
- 相談したい時はどうしたらいいんですか?
- 結局費用はいくらかかるの?
- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。
資産税務コンサルティング
相続税申告要否の自動判定
無料相談実施中
無料相談日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 午後 | ○ | × | × | × | × | × | × |
令和8年 2月 2日 ~ 2月 8日
営業時間
9:30~18:00
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
休業日
土曜日・日曜日・祝日
詳しくはお電話ください。
お問合せ・お申込み
0562-47-6697
お気軽にご相談ください。
詳細はこちら
お問合せはこちら
著書・執筆記事
過去の執筆記事
「近代中小企業」2009年5月号(【特集企画】銀行に頼らない経営)
「近代中小企業」2011年10月号(【特集企画】中小企業のためのガバナンス!)
「近代中小企業」2013年1月号(【特集企画】消費税10%突入に備える、転換期の経営防衛術)
「近代中小企業」2014年2月号(【特集企画】 社長の終活)
「近代中小企業」2015年12月号(【特集企画】直前緊急対策!マイナンバー制度)
バックナンバーのある号がございます。ご興味のある方はお問合せください。
詳細はこちら